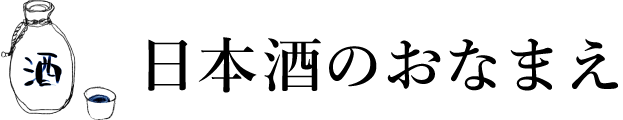「姿(すがた)」は栃木県栃木市のお酒です。
「姿(すがた)」の由来
「姿」を醸す飯沼銘醸は、栃木県栃木市西方町(にしかたまち)に位置します。
皆さんはその西方(にしかた)の地に昔から伝わる八百比丘尼(おびくに)伝説注1をご存じでしょうか。姿かたちが変わらぬまま八百年もの長い間生き続けた尼僧の伝説です。
ある時、八重姫という娘が誤って不老不死の薬を飲んでしまいます。その後、理由あって家を出ますが、知らない間に八百年もの歳月が流れます。家に帰る途中で自分の姿を池に映し出し、年をとっていない自分を知るのです。
八重姫が姿を映したこの池は、地元で“姿見の池”と呼ばれ、この池の名にちなんで日本酒・「姿」は命名されました。
「お酒は搾りたてが一番おいしい。濾過もせず、火入れもせず、そのままの姿を飲んでほしい。(九代目当主・飯沼氏)」という蔵元の想いも重なります。
注1:八百比丘尼(おびくに)伝説
昔、子供のない夫婦が神様にお祈りしていたところ、女の子を授かり、八重姫と名付けました。すくすくと育った八重姫は八歳の時、あやまって不老不死の薬を飲んでしまいます。
やがて十八歳になり美しく育った八重姫のうわさを聞いた帝が召し出そうとしますが、八重姫はそれを知って家を出ることにします。
里を離れた八重姫は山で会った白髪の老人と暮らし始めますが、両親が恋しくなり、家に帰りたいと告げます。すると老人はここを出ると二度ともどれないこと、自分が神様であることを告げ、姿を消してしまいます。
里に戻った八重姫は八百年も経っていることを知り、池に自身の姿を映してみますが、十八歳のままの姿でした。姫は尼になり、妙栄という名で巡礼の旅に出ますが、長く生き過ぎたとして若狭の海に身を沈めて命を絶ってしまいました。
参照:栃木県西方商工会HP
(http://www.nishikata-shokokai.com/local-information)
「姿(すがた)」ができるまで
飯沼銘醸は、現在の当主・飯沼徹典氏で九代目になります。八代目の頃までは新潟から杜氏さんを呼んで主に普通酒を造っていました。当時の代表銘柄は「冨貴(ふうき)」。八代目は毎月、蔵元のある西方地区から今市や日光の方まで営業に出ていましたが、「これからは特定名称酒注2を造りたい」と思うようになり、「杉並木」シリーズを造り始めます。
注2:特定名称酒
「特定名称酒」とは、「純米酒かどうか」「原料の米をどのくらい削っているか」という基準に則った日本酒のことで、それ以外を「普通酒」と言います。

日光の杉並木は約35キロメートルに渡り、世界最長の並木道としてギネス世界記録に登録されています。徳川家康の時代から20年にわたり、植樹された杉並木は、約400年経った今でも12,000本以上のスギが残っています。
毎月この杉街道を通っていた八代目が、杉並木をお酒の名前にしたのも納得です。


さて、「杉並木」と命名したものの、周りから“日光のお酒ですか?”と聞かれることが多くなります。確かに西方地区は日光の南方、宇都宮の南西に位置しますので正確には少し違います。
そこで新たに、厳選した西方のお米で、大谷川(だいやがわ)注3の伏流水を使用し、名前も西方地区に根付いた伝説に由来するお酒を造ろうと生まれたのが「姿」です。
現在、「杉並木」は栃木県内で販売され、「姿」は栃木のお酒として全国に流通しています。
注3 大谷川(だいやがわ)
栃木県西部、華厳滝から日光・今市の両市を流れて鬼怒川に合流する川。全長29km。
書体とボトルについて
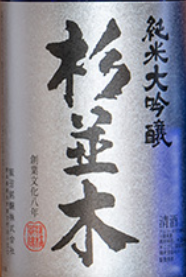
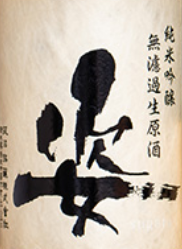
「杉並木」の書体は、まっすぐに伸びるスギの木を連想させるきっちりとした書体。
「姿」の文字は一目見たら忘れないくらいインパクトがあり、蔵元の強い想いが伝わってきます。
時々、遊び心が感じられるネーミングやラベルもあるので、どこかで見つけたら是非手に取ってみて下さい。
例えば近年では:


「うしろ姿」‐5種類のお米を使ったお酒の責めの部分のみをブレンドしたもの(ラベルを後ろから見た感じになっています。)
「がんばる姿」‐コロナに負けずに頑張ろうと応援の意味を込めて。
その他、「ヤマタノスガタ」‐8種類のお米を使ったので、8つの頭を持つヤマタノオロチに掛けたものなどがあります。

ボトルもユニークです。
左側はよく見かける日本酒のボトル。右側の四合瓶は “いかり肩”のような特徴のあるボトル。飯沼銘醸では右側のタイプを“首長ビン”と呼んでいますが、開栓後のそそぐ音に特徴があり、通常の“なで肩”タイプよりよい音がするそうです。
ただ、肩貼りと呼ばれる短冊のようなラベルが貼れないことが難点。その上、このボトルは2022年秋には製造中止予定とのことで、もし店頭で見かけたら、即ゲットして音を聞いてみて下さいね。
飯沼銘醸について
飯沼銘醸は、昔から肥沃な土地として知られる栃木市西方町にあります。
創業は文化八年(1811年)、200年以上も歴史のある蔵元です。
初代蔵元・飯沼岩次郎氏は新潟県長岡市(旧越路町)の出身。当時、出稼ぎで来ていた西方の地に飯沼銘醸を創業しました。創業当時の銘柄は「秋錦」。
長い間、飯沼銘醸も越後杜氏の元で、時代に即した酒造りを行っていましたが、時代は流れ、日本酒に求められるものも随分と変わってきました。飯沼銘醸でも、杜氏が引退した後は社長が製造責任者となり、今では高度な伝統技術を生かしつつ、時代に流されない独自のお酒造りを追求しています。
県外のお米も使用しますが、自社田を有し、市内7軒の農家や栃木農業高校とも契約して県内のお米を使ったお酒造りにもこだわっており、現在は地元の蔵人3人と共に、国内だけではなく韓国、香港、台湾、フランス、英国などにも輸出しています。

「お酒は全国各地にあります。そして皆さんは色んなお酒を飲みたいと思っているでしょう。その中で私たちは、印象付けられるようなお酒を造っていきたいと思っているんです。
一時は飲み疲れないお酒を造ろうと思っていました。それが「杉並木」かもしれません。でもただ“すっきりしておいしかった”というお酒だけではなく、印象に残るお酒も造りたい。材料、仕込み、味、みた目など全てが揃って初めてそんなお酒になるのではないでしょうか。」
飯沼社長の言葉です。
取材日:2022年1月15日
取材:ZOOMにて
取材協力:飯沼銘醸株式会社 九代目当主 飯沼徹典 代表取締役社長
画像提供:飯沼銘醸
取材後記:私が最初に「姿」に出会った時、“姿三四郎”と何か関係があるのかな?と思っていましたが、もっと深いお話があったとは!
飯沼氏は、開口一番、“ウチは他社さんのように面白いお話は特にないと思いますが・・・”とおっしゃっていましたが、なんの何の。杉並木にちなんだお話やボトルのお話、とても面白かったです。そして、最後のこんなお酒を造りたいというお言葉を聞いて、今後の「姿」がますます楽しみになってきました。
蔵元さんにとっては一番忙しい時期にも関わらず、取材を受けて下さった飯沼社長に感謝です。